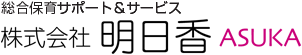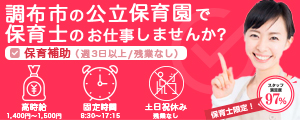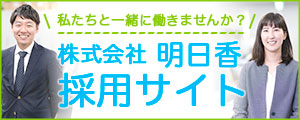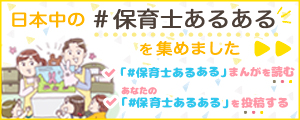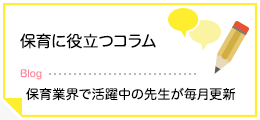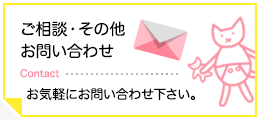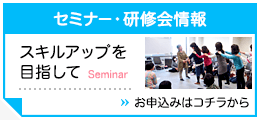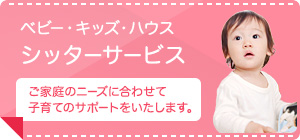ベビーシッター利用料負担が安くなる!ベビーシッター補助金とは?

ベビーシッターに高額で利用しにくい印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
実は近年ベビーシッターの利用に補助金が適用されるケースが増えおり、一時保育や病児保育などと同じような価格で利用可能なケースも増えてきています。
ここでは、そんなベビーシッターをお得に利用するための、補助金制度について詳しく説明します。
ベビーシッターが使えるケースや利用料金相場
ベビーシッターは、ご自宅、職場、ホテル、パーティ会場、病院など、お客様がご希望される場所でお子様を保育するサービスの総称です。
保育園や児童福祉施設の多くは、その施設で保育をするため、その点がベビーシッターとは大きく違います。
また、ベビーシッターの利用には、理由の制限は必要ありません。
お仕事はもちろん、リフレッシュ、保護者の病院への通院、結婚式への出席、旅行の付き添いなどあらゆる場面で活用することができるのもベビーシッターサービスの特徴です。
また、病児保育や病後児保育についても相談可能なベビーシッターは多いので、お子様の急な発熱と用事が重なってしまったなどの場合にも、素早く対応が可能です。
利用料金は利用されるベビーシッターサービスによって違いはありますが、おおよそ基本料金が1時間1,000円から4,000円程度となっています。
ベビーシッターの利用には基本料金の他、交通費やオプション料金、諸経費がかかることがあります。
具体的なベビーシッターの料金相場や、諸経費の金額や相場については、「ベビーシッター利用の料金相場はどれくらい?派遣やマッチング、個人事業で費用は変わる?」の記事に詳しく解説していますので、ご覧ください。
>>「ベビーシッター利用の料金相場はどれくらい?派遣やマッチング、個人事業で費用は変わる?」
ベビーシッター補助金とは?

ベビーシッターの補助金制度とは、ベビーシッターの利用料金を補助してくれる制度の事です。
利用料金が高額なイメージのあるベビーシッターですが、今、国や自治体の補助金制度を利用することで、非常に安価で使いやすくなっているのです。
例えば、東京都であればベビーシッターの補助金に50億円の予算が投じられており、補助制度が利用しやすくなっています。
これらの制度は、少子高齢化が進む中、女性の社会進出を助ける育児支援を発端としつつも、待機児童問題を解消するための大きな施策として、今後さらなる拡大が期待されています。
では、具体的にご家庭が使える補助金制度としてどのようなものがあるのか代表的な事例をもとにご紹介します。
国のベビーシッター補助金制度
国の管轄するベビーシッター補助金制度は公益財団法人全国保育サービス協会によって運営実施されています。
制度の概要は下記の通りです。
|
対象 |
労働者を1人以上雇用する企業の労働者(公務員の方は含まれません) |
|
手続きの仕方 |
割引券のご利用をご希望される保護者の方は、事前にお勤め先の会社と全国保育サービス協会との間での協定を締結されているか、事業主様にお問い合わせください。 割引券利用を希望する事業主様と協会との協定締結完了後、割引券が協会より会社に発券されますので、会社から割引券の交付を受けてください。 |
|
助成の対象サービス内容例 |
①幼児又は小学校低学年の児童(小学校3年生迄)の家庭内での保育、あるいは保育所等への送迎を行うこと。 ②残業で保育所等への送迎が出来ない時。 ③子供が病気で、保育所で預かってもらえない時。 ④母親が病気で、父親が子供の世話をしなければならない時。 ⑤会社復帰や就職の際、保育所への途中入所が出来ない時。 |
|
事業内容 |
ベビーシッター育児支援割引券 http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ 仕事も持ちながら子育てをするお父様、お母様を支援することを目的として、就労のためにベビーシッターを利用した場合、1日につき2,200円の割引が受けられる「ベビーシッター育児支援割引券」が発行されます。 双生児等多胎児家庭支援事業 http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ 小学校に就学前の双子や三つ子のお子様を育てていらっしゃる方への割引制度です。 年に2回9,000円の割引助成券が発行されます。 |
【参考:内閣府「「ベビーシッター派遣事業」の令和元年度の取扱いについて」より編集】
東京都のベビーシッター補助金制度
東京都では平成30年度から待機児童対策として、ベビーシッターの利用支援事業を実施しています。
現在(令和元年6月時点)では、まだ一部の市区町村に限られていますが、お住いの地域にて実施されている場合はご確認ください。
※対象地域
新宿区、台東区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、板橋区、葛飾区、三鷹市、府中市、国立市、東大和市
|
対象 |
1.保育所等の0~2歳児クラスに相当する待機児童の保護者 2.0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者(復職日以降、利用できます。) |
|
手続きの仕方 |
お住いの地域が東京都のベビーシッター利用支援事業を実施している場合、各お住いの区役所もしくは市役所のホームページの指示に従い、手続きを行なってください。 |
|
助成の対象サービス内容例 |
①認可保育園への入所ができず、仕事に復職できない時。 |
|
事業内容 |
対象の子どもが認可保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を1時間250円で利用できます。 (助成対象は保育料のみ。交通費等オプション料金等は助成対象外。) |
【参考:東京都「ベビーシッター利用支援事業」より編集】
地方自治体のベビーシッター補助金制度
ベビーシッターの利用については、各地方自治体にて独自の補助金制度があり、一部を抜粋して下記表にまとめました。
利用方法、支援内容については、各自治体のホームページ等から確認してみてください。
|
文京区子育て訪問支援券事業 |
文京区在住の2歳未満のお子様のお世話と家事の支援制度です。 http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/okosan/ichijiteki/sienken.html |
|
渋谷区育児支援制度「にこにこママ」 |
渋谷区在住で、妊娠している方、1歳未満の子育て家庭の方への支援制度です。 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/katei/children/ikuji/niko.html |
|
渋谷区病児病後児保育利用料金の助成制度 |
渋谷区在住で、お子様が病気やケガで保育施設に登園できない場合、 ベビーシッターを利用した方への助成制度です。1時間につき1000円が助成されます。 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/katei/children/ikuji/byojibyogo.html |
|
渋谷区ひとり親家庭支援制度 |
渋谷区在住で、中学生以下の児童を扶養しているひとり親家庭の方への支援制度です。 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/fukushi/general/hitorioya.html |
|
世田谷区子育て支援「さんさんサポート」 |
世田谷区在住で、妊娠している方、1歳未満の子育て家庭の方への支援制度です。 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/127/446/d00150939.html |
|
杉並区子育て応援券 |
杉並区在住で、0歳~5歳の子育て家庭の方への支援制度です。 |
|
新宿区ひとり親家庭家事・育児支援 |
新宿区在住で、義務教育終了前のお子様を扶養しているひとり親家庭の方への支援制度です。 |
|
港区ひとり親家庭支援制度 |
港区在住で、小学生以下のお子様がいるひとり親家庭への支援制度です。 http://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/hitorioya/index.html |
|
横浜市産前産後ケア事業 |
横浜市在住で、妊娠中や出産後5ヶ月以内で体調不良により育児等で支援が必要な方への制度です。 |
|
横浜市ひとり親家庭等日常生活支援 |
横浜市在住で、18歳までのお子様を扶養しているひとり親家庭の方への支援制度です。 |
|
鎌倉市在宅子育て家庭支援事業 |
鎌倉市在住の方で、在宅で子育てをされている方への支援制度です。 |
その他利用できるベビーシッター利用料補助制度とは?
ここまで国や自治体のベビーシッター利用補助について説明してきましたが、そのほか民間企業でも子育て社員への応援のため、補助制度がある場合があります。
急な残業や休日出勤などでもすぐに利用できるベビーシッター会社と提携し、サービスを利用しやすくしたり、利用した料金の一部を会社負担とするなど、ユニークな制度を取り入れる企業も増えています。
お勤めの会社にて制度が利用可能かどうか、確認してみると良いでしょう。
幼稚園や保育園への送迎だけでもベビーシッター補助金は使えるの?
ベビーシッターの依頼したいことの中で、多い依頼内容が「幼稚園や保育園への送迎」ですが、補助金を利用した場合、送迎については利用できる場合と、利用できない場合があります。
国の補助するベビーシッター補助金制度は、育児負担の軽減を軽減させる目的もあるため、送迎も利用の範囲内です。
一方、東京都で行われるベビーシッター利用支援はあくまで待機児童対策の一環で、保育園に入所できない間の支援なので、保育園にすでに入所できているお子さんには利用できません。
そのほか、各自治体の設置する補助金制度についても、依頼可能な場合と、そうでない場合とがありますので、送迎の目的で利用を検討されている方は、事前に確認しておくこと良いでしょう。
ベビーシッター補助金制度は今後増えていく傾向にある!

ベビーシッターは高額なイメージがあり、なかなか一般家庭での利用には敷居が高い印象をお持ちの方も多かったと思いますが、補助金などの活用で、今は利用しやすくなっています。。
ベビーシッターは、希望の場所に来てくれることもあり、保護者にとっても様々なシーンで子どもを預けることができ、非常に利用しやすいサービスと言えます。。
また、一方で待機児童対策として保育園をどんどん新設している自治体にとっても、すぐに導入でき、運用がしやすいベビーシッター補助金制度は増やしていく傾向が見られます。
現時点ではまだベビーシッター補助金等の制度がない自治体も、今後支援が決定することも期待できそうです。
また、働き方改革が叫ばれる中、労働力確保のために企業も子育て世代の家庭への支援に積極的に乗り出してきています。
お勤めの会社自体が制度を持っていなくても、福利厚生を委託している代行会社が割引制度を取り入れていることもあります。
ご自身がお住いの都道府県、または市区町村の公式ホームページやお勤めの会社の制度をうまく利用し、ベビーシッターを上手に使う方法を探してみましょう。
- 年度別
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度